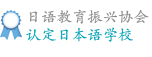代 珂
空から見た日本は、とてもきれいだった。海に囲まれている緑の木とその上に浮かんでいる白いの雲とが共存している静かな島だった。もっと広い世界を見たい、もっと素敵な人間と会いたい、もっとすごくなりたいという思いは、地面から離れているうちに、心と一緒に重く重くなりながら沈んでいた。「僕、うまくできるのかな」という未知の生活への不安でびくびくしている私の心は、その優しい景色のおかげでちょっと穏やかになった。
どこにいるにかかわらず、人は食事をするのだ。日本に来たばかりのものだから、そとで食事するのも当然だ。「そとで食べるなら、松屋に行こう。安くて美味しいだから。」と先輩に教えてもらったから、日本に来て二日目、わくわくしながら近くにある松屋に行った。
こっそりとそばの人を見ながら、販売機でチケットを買って、席に座って、そして店員にチケットを渡した。初めての異国での食事で緊張しすぎて、店員の挨拶までもぜんぜん分からない私の不安の様子は今思い出してもその緊張がよみがえる。店は実に静かだった。カウンターの裏側にいる店員が忙しそうに料理を作ったり片付けたりしているかわりに、皆は静かに食事して、ご飯を食べたりスープを飲んだり目の前の調味料を使ったりしていた。かちゃかちゃという台所からきこえる音と偶に出ている「いらっしゃい」と楽しそうに流れている歌を聴きながら、私は日本初の食事をしていたのだ。あの時そばに女の人が一人座っていた。最初はぜんぜん気付かなかったが、彼女が食事が終わった時、椅子からゆっくり立ち上がって、「ご馳走さま」と言った姿は、今も記憶に残っている。店員も「どうもありがとうございました」と返事をした。そして彼女が店から出た。一切はごく自然な感じで発生した。ほかの客も平然と食事をしていた。流れている音楽の中でたまにきこえる台所の音も店の雰囲気が変わってないことを証明しているように続いていた。しかし外国人としてあの一幕を目にした私には、これはまるで徹底的なショックだった。
いままでは、どんな店であっても、食事し終わった後お金を出して何も言わないで店を出るのは普通だと思っていた。たまに店のオーナーや店員などが「谢谢光临,欢迎再来(ありがとうございました、またいらっしゃい)」と言うが、客は何も言わずに出るのが当然だと思っていたのだ。だからこそ、ここで見たことはなんとも言えず心暖かく感じられた。その自然で心温かな場面に私は感動した。
「自分も言ってみよう」と決めた。わくわくしながら頭の中で何回も練習して、自分でもよく聞き取れないほど小さいな声で「ご馳走さま」を言ってみた。多分アクセントも変だし、声も小さかったと思うが、前にいる店員がちらっと私を見たのだ。そして、彼女が微笑しながら「ありがとうございました」と返事してくれた。
暖かい笑顔だった。私の心も。
それから、料理屋のことを大好きになった。留学生だから滅多に行かないが、行くたびに必ず「ご馳走さま」を言う。その暖かい雰囲気がいつも家で食事をしているように感じさせるのだ。だから始めてのアルバイトを料理屋にしたのは、このいきさつも原因の一つだと思う。
玲音という日本人夫婦でやっている小さい料理屋で働く、私は唯一の外国人だ。料理についてぜんぜん知らない私はゼロから勉強し始めた。お皿を洗うこと、台所を片付けること、麺をゆでること、お客さんのオーダーを聞くこと、一つ一つ店の先輩から教えてもらった。「店に来るのは大体近所に住んでいる人で、話したり美味しい料理を食べたりしに来ているから、緊張しないで頑張ってね」と店長さんが初めの日に言ってくれた。その最初の日のことも、今も覚えているのだ。心配しながら「いらっしゃいませ」を言うのは私だった。そして、「うまくできるかな」と言う声が再び心の中で響いていた。
お客さんがどんどん多くなってきた時、一生懸命覚えていた料理の名前や作り方も混乱してしまった。ミスがいっぱい出たが、私が外国人であることを知ているので、皆も許してくれた。お客さんの中に、話かけてくれる人もいた。「僕も業務関係で、よく上海へ出張するよ。すごい都市だな」とか「私の会社の近くに、日本語学校があって、中国人もたくさんいるよ」などとお客さんがいろいろ言ってくれた。店の雰囲気に慣れてきた私も皆との会話を楽しんでいた。そのなかで「私の兄弟の一人は今南京で仕事しているよ。あそこにも今日本人がいるんだ。いいことだね。チャンスがあれば、私も旅行に行きたい。ただの日本人として」という話が出た。一瞬の間、私は無言だった。今まで心の中に絡み合っているあるものが消えていた。その一言で。日本人と中国人の間、そんなに複雑ではない。料理について教えたり、楽しく話をしたり、旅に行ったりすることはできるのだ。だからこそ、「ありがとう」や「ご馳走さま」のような気持ちを、私は好きになったのだろう。だからこそ、広い世界も見るため、素敵な人間に会うため、大きな夢を持ってここに来たのだろう。その日、お客さんが帰った時、皆「ご馳走さま」と言ってくれた。私もあの時の店員のような暖かい笑顔で「ありがとうございます」と返事した。
あの頃から、「うまくできるかな」という声がどんどん去って行った。代わりに、お客さんからの「ご馳走さま」が毎日響いているのだ。
(拓殖大学主办「国际协力•国际理解赏作文比赛」最优秀赏受赏文章)